 会報
会報 なごやの大地を学ぶ会会報(no.52)
穀物の2つ目はムギです。麦はイネと異なり,乾燥した土と寒冷気候を好みます。小麦も大麦も多くのものに利用しています。麦茶,麦踏,ストロー,麦わら帽子,落穂ひろいなどムギに関わる言葉もよく耳にします。
 会報
会報  会報
会報  会報
会報  会報
会報 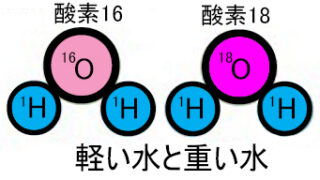 会報
会報  会報
会報 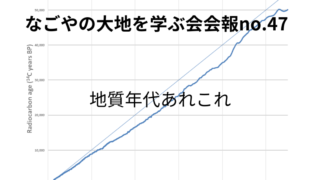 会報
会報 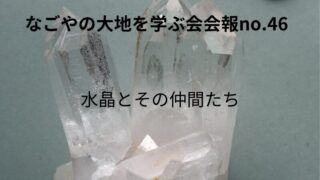 会報
会報 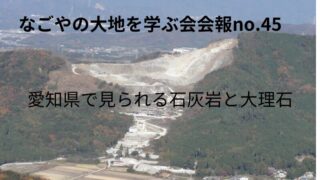 会報
会報  会報
会報