 資料
資料 資料014 八事裏山地域の地形・地質(概報)
名古屋市東部地域は猿投山塊東部から南へ尾張丘陵~知多半島まで続く丘陵の一部に含まれ,標高80~50m前後の定高性を持つ丘陵が見られる。今回,東山公園南部(八事裏山)と平和公園に残されている湿地や,乾燥化が進む湿地跡の保全・再生の可能性を求める調査が行われた。地質に関して若干の知見が得られたので,東山公園南部(八事裏山)地域について報告する。
 資料
資料  雑記
雑記 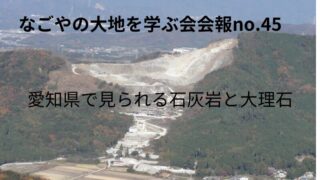 会報
会報 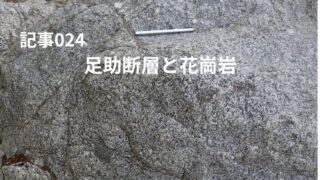 記事
記事  会報
会報  雑記
雑記  記事
記事  記事
記事  雑記
雑記  会報
会報