ソメイヨシノが咲き終わり,近所ではピンクと白の八重桜の並木が見られます。近くの川沿いの道や空き地には草花が咲いています。

スミレ(菫)Viola mandshurica
北海道から屋久島まで広く分布しています。日当たりのよい土手や野原,道路や山道沿いなどに自生しますが,写真は川沿いの道の舗装のひび割れから毎年顔を出しているスミレです(道路の舗装で多くが除去されてしまいました)。草丈は10cm前後で茎が極端に短いため,根から直接出ているようにみえます(根出状)。花は蝶形をした独特の形で,5枚の花びらは大きさが同じでなく,下側の1枚が大きいので,花の形は左右対称になっています。

ノゲシ(野芥子)Sonchus oleraceus
荒れ地や道端,土手,畑のあぜ,人家のまわりなどに自生します。ヨーロッパ原産ともいわれます。越年草(二年草)で,茎は太く,高さは50~100cm 程です。葉は羽状に粗く切れ込みが入り,葉縁には不規則に刺状の鋸歯がありますが,柔らかく触っても痛くありません。葉色は少し白っぽい緑色で光沢はありません。葉の基部は茎を抱き,その両端にある三角状の裂片は張り出して尖ります。花は黄色の小さな花がたくさん集まって,あたかもひとつの花のように見えます(頭花)。

ムラサキケマン(紫華鬘) Corydalis ncisa
日本全土や東アジアに広く原生し,雑草として繁茂しています。庭や林などの湿り気のある日陰に生えるといわれますが,写真のものは日当たりのよい空き地で撮ったものです。1年以上2年以内の2年草で,発芽した年は開花せず,その年の冬に地上部が無くなり翌春,芽吹き開花するそうです。

ホトケノザ(仏の座) Lamium amplexicaule
シソ科オドリコソウ属の一年草です。春の七草の「仏の座」は,キク科の「コオニタビラコ」という植物で,これとは違います。葉は対生で,縁に鈍い鋸歯があり,下部では葉柄を持ちます。茎は段々につくことから,サンガイグサ(三階草)とも呼ばれます。上部の葉脇に長さ2 cmほどの紫で唇形状の花をつけます。上唇はかぶと状で短毛がびっしり生え,下唇は2裂し,濃い紅色の斑点があります。

ナガミヒナゲシ(長実雛芥子)
Papaver dubium
丸みのある淡赤色の花が咲く外来植物で,繁殖力が強く,繁茂・群生するため在来植物に影響を及ぼします。花の色はオレンジ色(淡赤色)で花弁は4枚です。真ん中の子房が円筒形で長く出っ張っているのが特徴です。葉には細かく切れ込みが入り,茎には硬い毛が生えます。触ると手がかぶれる恐れがあるそうです。後でできる実が長いので「長実」と名付けられたそうです。
キンメツゲ(金芽柘植)Ilex crenata
これは樹木です。モチノキ科のイヌツゲの園芸品種で常緑樹です。新芽がキラキラと輝いています。イヌツゲより小さくて密生しやすいため,生垣などに向いています。葉は長さ1~2cmの楕円形で革質で,枝から互い違いについています。縁には細かなギザギザがあり,両面ともに無毛です,裏面には腺点と呼ばれる小さなツブツブがあります。


撮影は2025年4月17・18日です。場所は名古屋市昭和区。花の名前はgoogle画像検索で調べました。怪しげなものはご連絡いただけると幸いです。
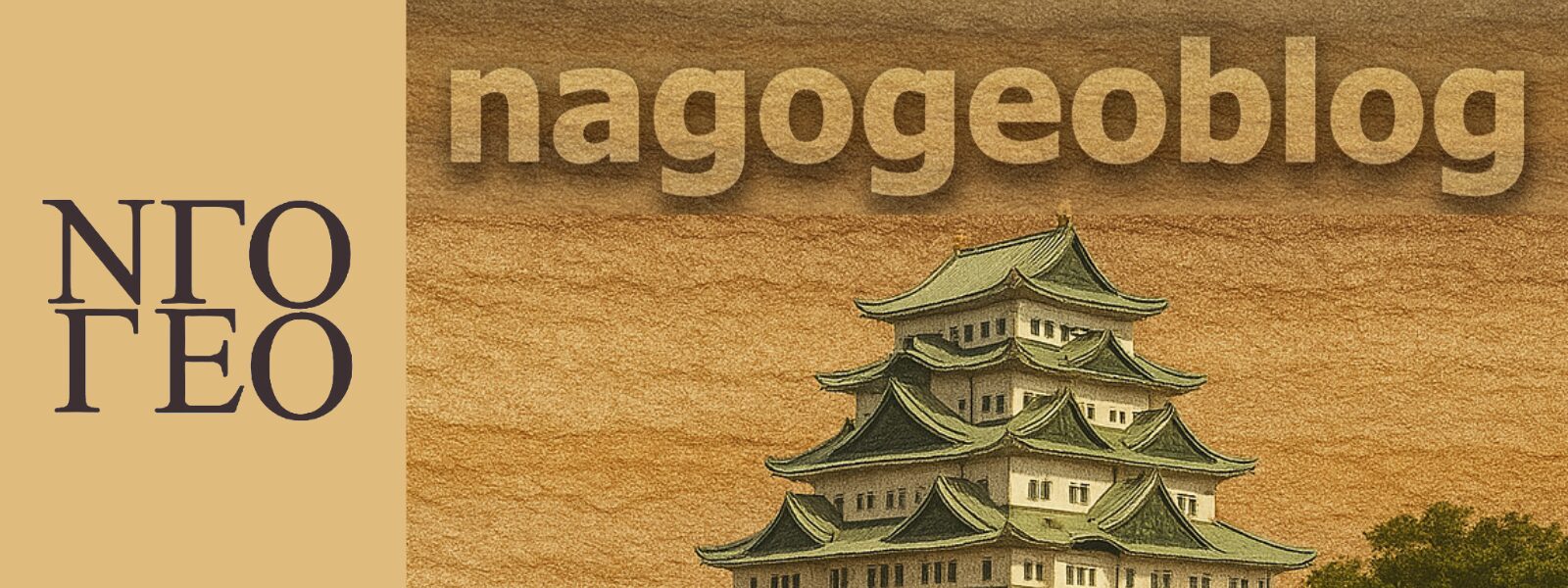

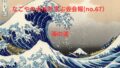

コメント